家解体時の廃棄物はどう処理する?正しい処理方法を紹介

不要になった家を解体すると、屋根材や壁材、室内にあった家具・家財など大量の廃棄物が発生します。これらの廃棄物は、然るべきルールに則って処理しないと法律違反になってしまう恐れがあるので気を付けましょう。
また、廃棄物の処理は自分で行えるものと、業者に頼まなければならないものの2種類があるため、取り扱いにも十分な注意が必要です。
今回は、家の解体を検討している方向けに、解体時に発生する主な廃棄物の種類と、廃棄物処理に関するルール、廃棄物の処理方法、処理費用を安く抑えるコツをまとめました。
家を解体するときに発生する廃棄物の種類

家を解体する際に発生する廃棄物は多岐にわたりますが、素材別に分類すると以下のようなものが挙げられます。
| 廃棄物の種類 | 発生源 |
|---|---|
| 木くず | 木造住宅の柱や梁、床材、壁材など |
| コンクリートがら・アスファルトがら | 家の基礎部分や土間、外構(駐車場や塀など)など |
| 金属くず | 住宅の構造材や屋根材、窓枠などに使われる鉄筋や鉄筋、トタン、アルミサッシなど |
| ガラス・陶磁器くず | 窓ガラス、便器、洗面台、タイル床など |
| プラスチック・ビニール類 | 断熱材の一部や塩ビ管(水道管)、雨どい、床材(クッションフロアなど)、壁材(ビニールクロスなど)など |
| 石膏ボード | 壁や天井などの内装材 |
上記で挙げた廃棄物のほとんどはリサイクルすることが可能です。そのため、家を解体した際に発生した廃棄物はきちんと分別し、然るべき方法で処理することが求められます。
家解体時の廃棄物は一般廃棄物?産業廃棄物?
廃棄物は大きく分けて産業廃棄物と一般廃棄物の2つがあります。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、以下7つに分類されるものを指します。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- その他政令で定める廃棄物
これらの廃棄物を処理するためには都道府県の許可が必要になるため、一般の人は自分で処理することはできません。一方の一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物全般のことです。
一般廃棄物はさらに、産業廃棄物として規定されない事務所などから排出される事業系一般廃棄物と、一般家庭から排出される家庭廃棄物の2つに分類されます。
では、家解体時に排出される廃棄物はどちらに該当するのかと言うと、ケースによって異なります。具体的には、家の解体に伴ってあらかじめ室内にあった家具や家財などを自ら処分する場合は、一般廃棄物として処理することが可能です。
一方、家の解体を業者に依頼した場合、解体は事業活動の一環であるため、廃棄物は上記に挙げた産業廃棄物か、事業系一般廃棄物(事業活動に伴って排出したもののうち産業廃棄物でないもの)扱いとなります。
廃棄物処理に関する法律やルール
廃棄物の処理には、さまざまな法律やルールが適用されます。知らずに家解体時に出た廃棄物を処理すると、法律違反と見なされる可能性もあるので注意しましょう。
ここでは家解体時に知っておきたい廃棄物処理に関する主な法律とルールを3つに分けて解説します。
廃棄物処理法
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)とは、廃棄物の適正な分別・保管・収集・運搬・再生・処分などを行う際のルールを取り決めた法律です。
一般廃棄物および産業廃棄物の処理方法などのルールが規定されており、家解体時の廃棄物はこの法律に則って処理するのが基本となります。また、廃棄物の排出事業者の責任や、不法投棄の禁止などについても規定されています。
建設リサイクル法
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、建設工事や解体工事で発生する廃棄物を正しく処理し、リサイクルを促進することを目的とした法律です。建設工事や解体工事に携わる事業者に対し、特定建設資材の分別解体およびリサイクル化を義務づけています。
また、当該法律の対象となる工事を行う場合、都道府県への届出が必要になる旨も明記されています。
アスベストに関する法令
アスベスト(石綿)はかつて建物の断熱材や保温材、防音材などとして用いられていましたが、健康を害するリスクが高いことから、昭和50年に原則禁止となりました(※)。
しかし、それ以前に建設された建物にはアスベストが用いられている可能性があることから、古い家を解体する際はアスベストに関する法令を遵守して作業に当たる必要があります。
家解体時に適用されるアスベスト関連法令については、大気汚染防止法や大気汚染防止法施行令などが挙げられます。上記の他にも、自治体によっては家の解体時に適用される条令が設けられている場合があるので、あらかじめ役場などに問い合わせておくとよいでしょう。
家を解体するときの廃棄物の処理方法

家を解体するときに出た廃棄物の処理方法は、業者に依頼する方法と、自分で処分する方法の2つがあります。前者の場合は解体業者に依頼することになり、解体から処理までまとめて任せられるところが利点です。
なお、業者に任せた場合、解体時の廃棄物は一部を除いて産業廃棄物扱いになります。産業廃棄物は都道府県の許可を得た業者でなければ収集・運搬・処理できないため、許可を得ているかどうかきちんと確認しましょう。
一方、家の解体時に建物の所有者が残した廃棄物(残置物)については、家の所有者に処理責任があります。そのため、家の解体を業者に依頼した場合でも、残置物に関しては事前に自ら処理しなければなりません。
自分で残置物を処理する方法には以下のようなパターンがあります。
- 粗大ごみとして処分する
- リサイクルショップに買い取ってもらう
- フリマやインターネットオークションで個人売買する
- 不用品回収業者に引き取ってもらう
2や3は廃棄物を処理すると同時に臨時収入を得られる可能性があるという利点があります。ただし、状態の良いものでなければ買い取ってもらえないため、売れないものは1や4で処分するのが一般的です。
コストを節約したいのなら粗大ごみに出すのがおすすめですが、量が多い場合は排出の手間がかかります。また、自治体によっては手数料がかかったり、一度に排出できる量やサイズに制限を設けていたりするケースもあります。そのため、家の解体に伴って大量の廃棄物が出る場合は、不用品回収業者にまとめて引き取ってもらった方が楽でしょう。
家解体時の廃棄物処理を安くするコツ
家解体時の廃棄物処理のコストをできるだけ安く抑えるコツは大きく分けて4つあります。
- 相見積もりを取る
- 不用品を買い取ってもらう
- 補助金・助成金を利用する
- 業者に直接依頼する
家の解体および廃棄物処理の費用は業者ごとに異なります。なるべく複数の業者から見積もりを取り、より良い条件を提示してきた業者に依頼すればコストを節約できるでしょう。
なお、解体業者への依頼は工務店やハウスメーカーを介して行うことも可能ですが、ほとんどの場合中間マージンが発生するので、自分で業者を探して直接依頼した方がコストを削減できます。
また、残置物の処分費用は量が多いほど割高になるので、買取可能なものはなるべくリサイクルショップに持ち込むか、フリマやインターネットオークションを活用して処分しましょう。
以上が廃棄物処理のコストを安く抑える基本ですが、さらに自治体によっては補助金や助成金を活用できる場合があります。補助金・助成金の有無や内容、要件は自治体によって異なるので、家を解体する際は事前に役場に問い合わせておくことをおすすめします。
家解体時に出た廃棄物の正しい処理方法を知っておこう
家解体の際に排出された廃棄物は、各法令や条令に則って正しく処理する必要があります。家の中にある残置物は、一般廃棄物として家の所有者自らが処分する必要がありますが、解体の際に排出された廃棄物は、産業廃棄物もしくは事業系一般廃棄物となります。許可を得た業者に、収集・運搬・処理を委託しましょう。
未許可の業者に依頼すると、その業者だけでなく、処理を委託した側も法令違反に問われるリスクがあるため、家の解体および廃棄物の処理を依頼する業者は信頼できるところを選びましょう。


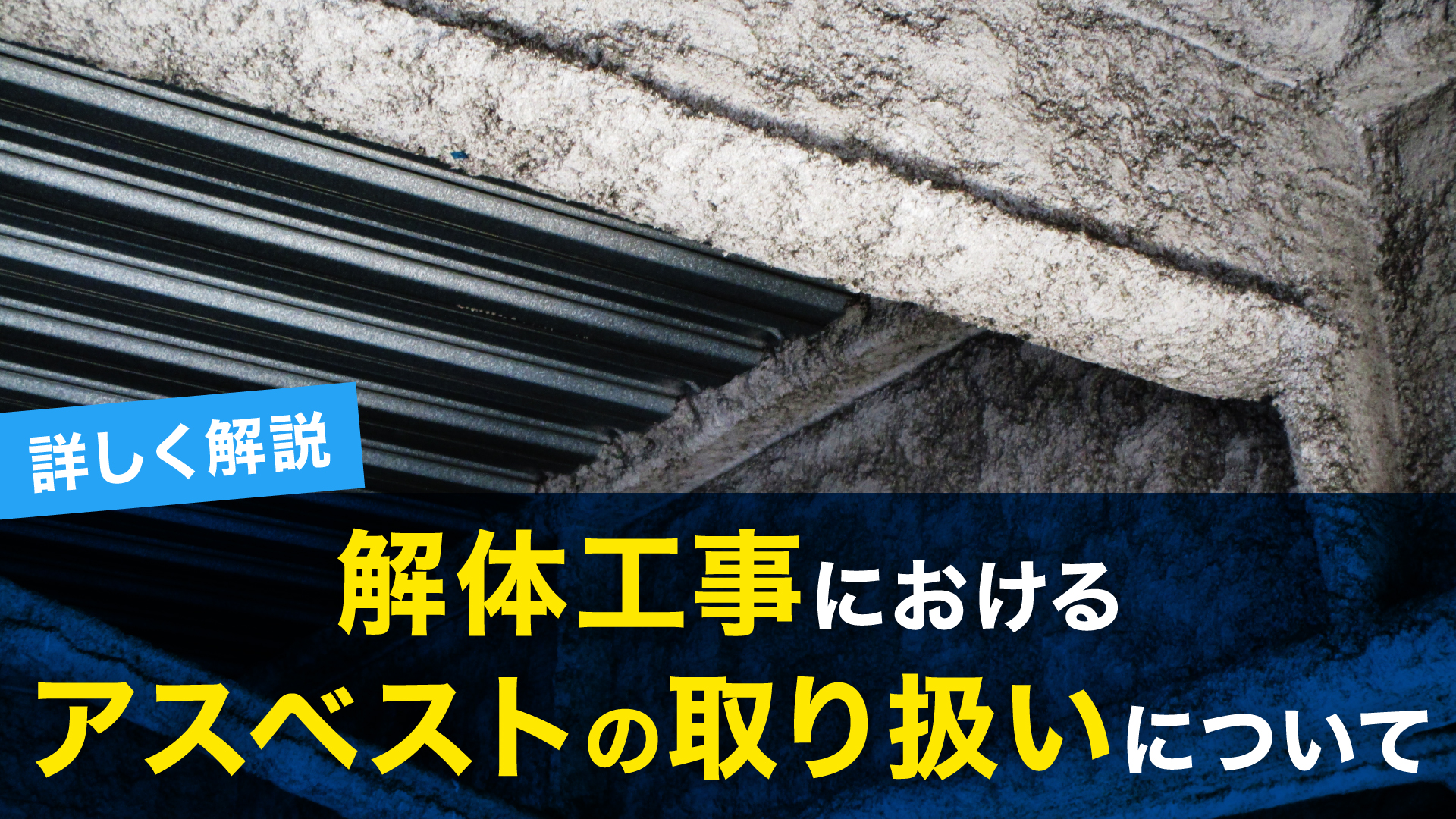
の種類と処分費について_01.jpg)
