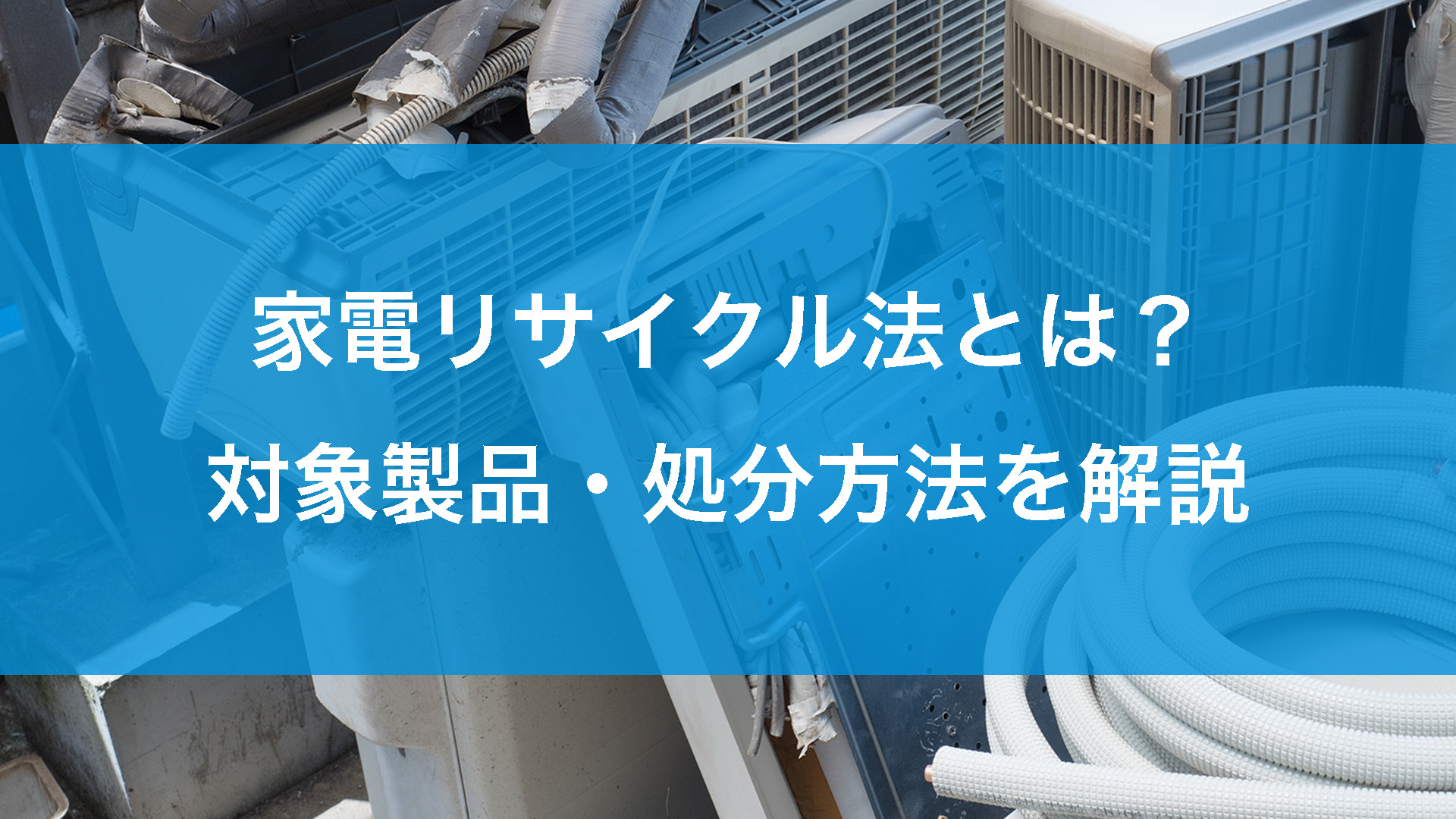小型家電リサイクル法とは?対象製品や産廃になるのかを解説

テレビや洗濯機、冷蔵庫やエアコンといった家電製品については、処分する際にリサイクル料金がかかるようになったため、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)はご存じのことでしょう。
ところが、小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)についてはよく知らないという方も多いのではないでしょうか。本記事では、小型家電リサイクル法について、施行の背景から処分方法まで解説します。
小型家電リサイクル法とは?
小型家電リサイクル法とは、使用済みの小型家電の再資源化を促進するために、廃棄物の適正な処理および資源の有効な利用の確保を図ることを目的として2012年に制定された法律です。
家電リサイクル法が対象としている4品目を除く28類型の品目を小型家電リサイクル法の対象として政令で指定しています。ケーブルや充電器などの付属品も含めて、ほぼすべての品目が小型家電リサイクル法の対象となっていますが、対象外の品目もあります。
対象外品目としては、太陽光パネルなどの特殊な取り外し工事が必要なものや、破損しやすく特別な収集運搬を必要とする蛍光管や電球です。通常家庭で使用する小型家電については、基本的にすべて小型家電リサイクル法の対象だと考えるとよいでしょう。
施行の背景と課題
2012年以前において、大型家電や自動車などは再資源化率が7割~9割という高水準にありましたが、デジタルカメラやゲーム機といった小型家電は、廃棄物として市町村にて埋立処分されるのが一般的でした。埋立処分される小型家電にも、鉄やアルミニウム、レアメタルといった有用な金属が含まれています。
鉱石52.8kgから採取される金の量は48mgであり、同じ量の金が140gの基板1枚から採取できるともいわれています。有用な金属を含む使用済み小型家電が大量に廃棄されている状況を疑問視し、使用済み小型家電から金属を回収して再利用するために提唱された考え方が「都市鉱山」です。
都市鉱山とは、都市の廃棄物から金属を回収する様を、鉱山での採掘に例えたものです。埋立処分されている使用済み小型家電から有用な金属を回収するための制度が検討された結果、小型家電リサイクル法の制定に至りました。
使用済み小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針において、回収量の目標を設けて取り組みを進めてきましたが、2015年度および2018年度の時点で目標を達成できず、達成期限を2023年度まで再々延長しています。
小型家電のリサイクルの現状
2012年に小型家電リサイクル法が制定されてから、小型家電の回収量は増加しています。2013年度の回収量は23,971トンでしたが、2020年度の回収量は102,489トンと4倍以上になりました。環境省・経済産業省から認定を受けた認定事業者によって再資源化された金属は、2022年度は52,222トンであり、金額換算すると70.4億円に相当します。
一方で、回収量の目標は2023年度までに年間140,000トンであり、2020年度時点で目標値の73%に留まっています。年間140,000トンの目標を達成するための1人当たりの回収量は年間約1kgですが、全国平均は532gであり、1人当たり1kg以上の回収量を達成しているのは12県に過ぎません。依然として無駄になっている資源が多いのが現状なのです。
参照:
小型家電がリサイクル事業者のもとに回収された実績(環境省、令和2年度)
小型家電リサイクル法の対象製品

小型家電リサイクル法が対象とする「使用済小型電子機器等」とは、小型家電のうち、使用が終わったものをいい、中古品として販売する場合などは除きます。このため、家庭で使わなくなったとしても、引き続き使用可能な状態でリユース品として中古品買取店などに引き渡すときは、小型家電リサイクル法の制限を受けません。中古品の売買においては、従来どおり認定事業者以外にも引き渡すことが可能です。小型家電リサイクル法では小型家電を細かく分類しており、対象となる28品目は次のとおりです。
小型家電リサイクル法の対象製品
- 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
- 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
- ラジオ受信機及びテレビジョン受信機
- デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具
- デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具、光ディスク装置その他の記憶装置
- パーソナルコンピュータ
- 磁気ディスク装置
- プリンターその他の印刷装置
- ディスプレイその他の表示装置
- 電子書籍端末
- 電動ミシン
- 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
- 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
- ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
- 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
- フィルムカメラ
- ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具
- 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具
- 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具
- 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
- ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
- 電気マッサージ器
- ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
- 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
- 蛍光灯器具その他の電気照明器具
- 電子時計及び電気時計
- 電子楽器及び電気楽器
- ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具
※ 3、17、18、19 については、家電リサイクル法の対象となる製品は除く。
小型家電リサイクル法の流れ
小型家電リサイクル法におけるリサイクルの流れは次のとおりです。
- 消費者または事業者は、市町村・認定事業者・小売業者(家電量販店など)を通じて小型家電を排出
- 認定事業者が回収
- 中間処理施設にて破砕・選別などを経て高度に分別
- 金属精錬を行って循環利用する
以上が小型家電リサイクル法がイメージする流れです。環境省の通知(環廃企発第1303083号)においては、各段階において関係者が積極的にリサイクルの取り組みに参加することが求められており、その役割についても言及されています。
消費者および事業者は適切な排出に協力すること、市町村は分別収集を行うこと、小売業者は消費者の適正な排出に協力することなどが明記されています。認定事業者については、廃棄物処理業の許可が不要とされており、その代わりに再資源化事業計画を作成して主務大臣の認定を受けることが必要です。
小型家電リサイクル法は、リサイクルを促進する制度として構築されていることから、認定事業者には広域的回収による規模の経済を働かせた再資源化事業を実施することが期待されています。
認定事業者とは?
認定事業者とは、使用済みの小型家電の再資源化を適正に行える者として、小型家電リサイクル法第10条第3項の認定を受けた者です。認定事業者は、市町村が分別して収集した使用済み小型家電や事業者が排出する使用済み小型家電を引き取ってリサイクルを行います。
区域内の市町村が分別して収集した使用済み小型家電について引き取りを求められたときは、天災で引き取りが困難な場合などのやむを得ない理由がない限り、引き取る義務があります。小型家電を排出する際は、無許可業者の行う廃品回収などを利用しないように注意しましょう。
小型家電リサイクル法に基づく回収であるかどうかは、マークの有無で確認できます。認定事業者は「小型家電認定事業者マーク」を、市町村または市町村の委託先は「小型家電回収市町村マーク」を表示しています。迷った場合はマークの有無を確認してみましょう。
家庭で出た対象製品の処分方法

小型家電リサイクル法第6条では、市町村、認定事業者または認定事業者から委託を受けた小売業者などに引き渡すことを消費者の努力義務として定めています。
市町村による回収については、2019年時点で、全国1,741市町村のうちの1,390市町村(79.8%)で実施しています。「実施していない市町村が20%もあるの?」と感じた方もいるでしょうが、居住人口ベースで見ると回収を実施している市町村は94.2%に上るため、市町村の回収を利用できずに困ることはほとんどないでしょう。
回収方法や回収品目は各市町村で異なるため、お住まいの市町村のWebサイトをご確認ください。認定事業者による回収については、宅配便を利用した回収や拠点回収があります。
小売業者による回収については、大手家電量販店のほとんどで店頭回収などを実施してます。小型家電の回収を実施している認定事業者・小売業者については、一般社団法人 小型家電リサイクル協会のWebサイトにて紹介されていますので、参考にしてみてください。
事業活動で出た対象製品の処分方法
小型家電リサイクル法第7条では、事業者が使用済み小型家電を排出する場合は認定事業者に引き渡すことを努力義務として定めています。これまでと同様に産業廃棄物処理業者に引き渡すことも可能ですが、循環型社会を構築するという観点からは、認定事業者への引き渡しを第一としたいところです。
なお、事業者が排出する使用済みの小型家電は産業廃棄物に分類されるため、家庭で処分する場合と異なり、市町村によるボックス回収や小売店への持ち込みなどは利用できません。事業者が小型家電を排出する場合は、認定事業者または産業廃棄物処理業者に引き渡しましょう。
認定事業者に引き渡す場合でも、委託契約書の締結やマニフェストの発行などが必要な点は変わりません。小型家電の排出時のルールは、通常の産業廃棄物と変わらない点に注意してください。
SDGsの観点から見た小型家電の処分
2015年9月の国連にて国際目標としてSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)が採択されましたが、産業廃棄物の排出についてはSDGと大きな関わりがあります。SDGsの目標12として「つくる責任つかう責任」が設けられており、目標12のターゲットのひとつには「2030 年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する」があります。
産業廃棄物の排出の観点からは、事業者として小型家電を認定事業者に引き渡すことは、このSDGsのターゲットにも適う取り組みです。小型家電の引き渡し先を産業廃棄物処理業者から認定事業者に変えるだけであり、どのような事業者でもSDGsに向けた取り組みとして実行できます。
産業廃棄物処理業者かつ認定事業者という場合もあるため、知らない内にSDGsに適った排出をしている可能性もあります。「SDGsに関する取り組みをしたいものの、自社で何ができるかわからない」という場合、まずは小型家電の処分方法から見直してみてはいかがでしょうか。
まとめ
小型家電リサイクル法についての解説でした。家電リサイクル法のようにリサイクル料金が課されている訳ではないため、普段の生活において小型家電リサイクル法は意識しにくい部分があります。
しかし、有限な資源で豊かな暮らしを続けていくためには、小型家電のリサイクルは欠かせません。国が目標とする回収量は1人1年当たり約1kgであり、個々のわずかな協力で達成できる量といえます。個人・事業者ともに、まずは処分方法の再確認から始めてみませんか。